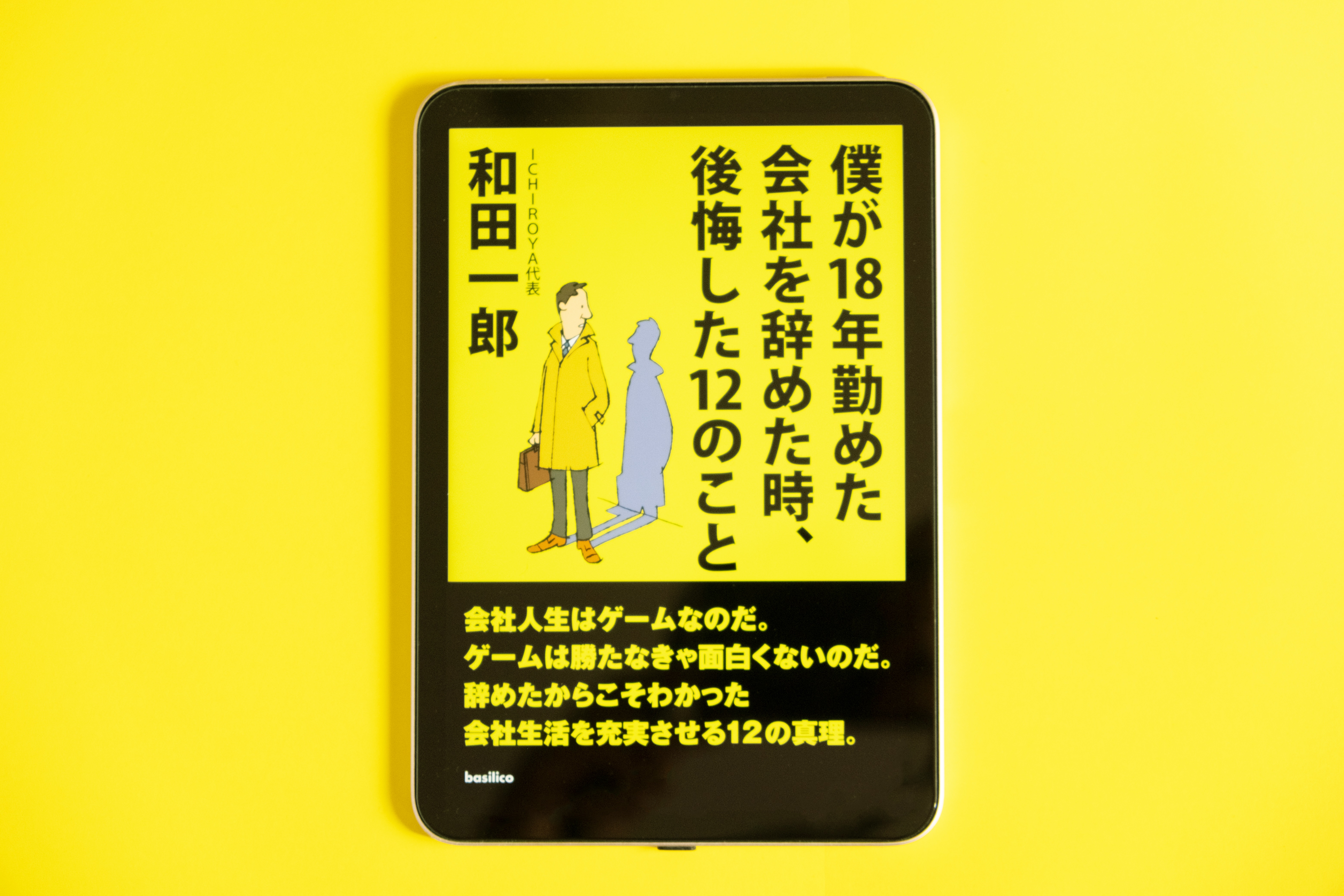
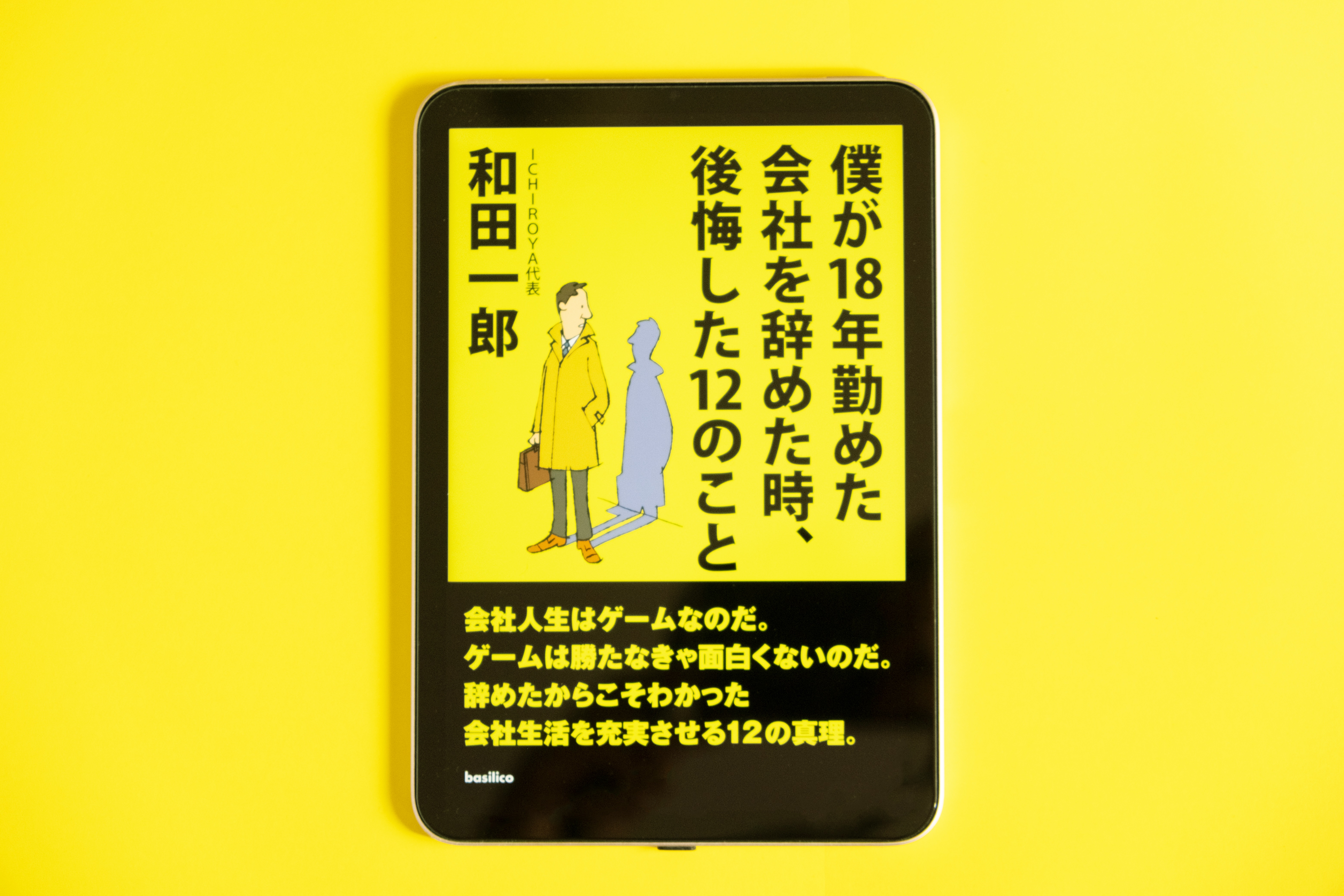
数年前に読んで、折に触れて思い出す書籍があります。
僕が18年勤めた会社を辞めた時、後悔した12のこと | 和田一郎著(出版社:バジリコ)。
タイトル通り18年勤めた会社を辞めた男性が、会社勤めの時のことを振り返りつつ事を綴っています。
名著です。この先、何者にもなることはできず、居場所がなくらない限り会社勤めをしていくだろう自分にとって、もっと若いうちに読んでおけばと痛感する書籍です(若い頃にリアリティをもって読むことができるかは疑問ですが)。
日系企業に勤めた一人の人間の心象風景を的確に言語化していて、胸に迫ります。
この方が入社し出世競争を経た時代と今の社会情勢がまったく同じではないことは承知の上で、あと僅かで40の声を聞くおっさんが読書感想文を書いてみたいと思います。
今の自分にぶっささる
今の自分にぶっささる。ぶっささりまくる。
それは私がもう40の声を聞く年齢になったからです。
この本の著者が会社を退職したのが42歳。この年齢がリアリティをもって私に迫ってきます。
私が若手社会人だった頃や今現在、どういった人物か簡単に箇条書きしてみます。
- 会社の行事や些細なことに真剣になれなかった
- 会社に人生の時間を奪われている感じる
- なぜ労働者側から役員等を評価しそれ相応の処遇を与えられないのか。仕組みが異常だと思っていた…
- 競争に晒されたことがない。シビアな打ち合わせをした経験が少ない
- 我々(労働者)がいるから利益を得ることができるのだ、上から目線をするなと奥底で思っていたことがある
- 会社は好きではないが、今の業務は好きである
- 自発的にリーダーになった経験がない

改めて振り返ると本当に禄でもありませんね
そしてそして、今。
この先会社員として大逆転はないと理解しています。現実は漫画のようにはいきません。
もっというと、組織に残った先に飼い殺しになることも覚悟していかないといけません(組織が存続していくだけの力があるのが前提ですが)。
著者も言っていますが、若い頃に言われた助言って真剣に受け止めることができず「自分だけは違う」と思いがちなんですよね。
私も、そうでした。ほんと小生意気ですね(苦笑)。
若者に一度読んでほしい書籍だけど、ほとんどに若者は興味を持たないであろう書籍とも言えます。
大事なことはいつも遅れて気付くことになるのが、人の世の常なのでしょう。
誰も本当の事は言ってくれない
著者が入社時に怒られたエピソードが著者の当時の性格を表すのに秀逸です。
そしてこのエピソードが首がもげるほど頷けるのです。著者の方に大変失礼かも知れませんが、私も同じタイプです…。
ついでに私のエピソードも記しておきます。
学生時代のことです。今も変わらないと思いますが、クラス全員が何らかの委員(図書委員とか)にならないといけず、各々の委員を決めるホームルームでの事でした。
私は当時あまりにも抜けていて、クラス替えで変わった新しい担任の言葉なんて聞いておらず「どうせ委員決めは去年のクラスと同じようなものでしょ」と上の空。別のことをぼんやり夢想していました。
もちろん前年と同じ決め方のはずもなく、自分がぼーっとしている間に委員はあっという間に決まり、残っているのは誰もやりたがらない人気の無い委員でした。
みんな口では言わずとも抜け目なく、自分が有利になるようにしっかり担任の話を聞き、行動していたのです。
こんな事は当たり前すぎていちいち誰も説明してくれません。自分は本当に間抜けであまりに無防備だったのです。
…これ、うまく伝わっているでしょうか?
今振り返ると、社会人だろうが学生だろうが、こういう部分に性格がでるのだろうなと実感します。
みんな口には出さないけど、虎視眈々と何かを考え何かを狙っている。そういうことをまったくわかっていない人間でした。
もうとっくの昔に、誰も本当の事は言ってくれない世界で暮らしているのです。そのことに気付くことにも遅れをとっていました。
「後悔した12のこと」を読み共感したこと
著者は本の中で後悔した12のことあげています。
12のことはどれも共感できることばかりなのですが、より実感を伴って「めちゃんこわかる!」と個人的に思ったことが何点かありました。

私の主観がかなり混じります(一応、念のため)。理解出来ない、という人もきっといるはず
- ゴルフを始めればよかった
- 社内の人間関係にもっと関心をもてばよかった
- もっと勉強すればよかった
ゴルフは始めておいて損はありません。始めるのは若ければ若いほど良いと感じます(私はもう手遅れです(苦笑))。
陰キャの私でも想像出来ます。仕事関係者とゴルフに行けば顔と顔が繋がります。仕事がやりづらくなるなんてことはないでしょう(粗相さえしなければ)。幹事になればちょっとした企画をしたり、全体を見る気配りだってしなければなりません。
ゴルフ中でなければ聴けない話だってあるでしょう。
権力や決裁権をもっているのはゴルフを嗜む年配者という事実もまだあるでしょう。
(それに、ゴルフをしている方がなんだかパリッとしているような気がします。気がするだけなんですが、そう感じてしまうのは私が昭和生まれの人間だからでしょうか)
身体も動かしつつ、仕事以外の能力も求められ鍛えられる。会社員生活を充実させるのにけっこう大事なことだと感じます。
「仕事さえしっかりやっていれば人間関係なんてどうでもいいっしょ」が通用するのは漫画の中だけです。
令和の時代とはいえワンマンのよう会社なら「喫煙所や酒席で大事なことが決まる」ことだってまだまだあるはずです。
残酷な話ですがみんながみんな大きな企業に入社し、生き生きと仕事が出来るわけではありません。狭い社内の意味不明なローカルルールが肌に合わないことだってあります。
人間関係を築くのが苦手だった私は、せめて業務時間内に「興味のあるふり」をすることから始めて訓練していけばよかったと痛感します。
自分が関心をもてば、相手だって多少は自分に関心をもってくれるはずです。
過剰に期待せず、どこかのタイミングでwin-winくらいになればいいなぁの感覚で最初からいけばよかったと思います。
勉強はした方が良いのはいうまでもないことでしょう。著者も書いてますが、勉強の仕方を間違えてはいけませんが。
2015年に発行された書籍ですが、さすが会社員の世界の荒波にもまれてきた著者、「勉強」についての助言が今なお身に沁みます。
個人的に思ったのが「歴史」は勉強も結構大切なのではないかということでした。
「人間の歴史」や「人間が発案し興した集団の最後」等の歴史です(縄文弥生時代とかではなく近代史あたり)。
会社員とはいえ人間万事塞翁が馬というか盛者必衰の理を知っておく必要性もあるのでは、と。
人間は集団を形成するとどのように蠢いていくのか、これって「社内の力学」にも応用できそうですよね。
繰り返す人間の歴史を予習しておけば、自分の身に「その時」が来たとき、多少なりともショックを和らげ精神衛生を守ることができるかもしれません(苦笑)。
うん、笑えん。
【追記】
そういえば書き忘れていたので追記。
お酒の知識もあるに超したことはないと、そう感じます。ちょっとしたお酒の作り方や作法などです。
日本酒・洋酒など、さわりだけでも知っておいてマイナスになることはないかと。
はい、時代錯誤だと頭ではわかっています。なのでこれは「個人的に感じたこと」です。
お酒を飲まない人は「酒飲み」の信条を理解し難い部分もきっとあります。わりかります。
未だに私は「熱燗」と「冷や」を分ける理由がわかりません。
もしかするとお酒の席で、仕事上で接するだけでは知ることができない上司の別の顔、他部署の人の身の上話など知り、仕事を進めていく上での予備知識が増えるかもしれません。
当たり前ですが、会社員は人間です。
共感した番外のこと
著者と同じで宴会や忘年会の会場に行くのが嫌で嫌で仕方ない人間です。
これは慣れることはなく、今後も改善する見込みはないと思います。ただ歳を重ねたせいか楽しそうなふりは出来るようにはなりました。
また、口下手で突然司会の様なことをふられるとしどろもどろになってしまいます。
臨機応変に対応し話すことができる人間を見ると「ああ、出来が違うのだな」と思い知らされます。
ゲームの勝敗の帰趨 – それでも人生は続いていく
会社員必読の書ではないでしょうか。
読む人は「会社員というゲーム」の中の自分の立ち位置を再確認することになります。
今読み返してみても「わかる!」と頷くこと請け合いです。
格好いい言葉が並んでいるビジネス書を読むのも大切ですが、著者の方も含め市井に生きる生身の人間が綴った普遍的は事実は忘れてはいけいないことと思います。
この記事の終わりの文章を書こうとしたら朝井リョウ氏の「何者」という小説が頭に浮かびました。
余談ですが「何者」って言葉、めっちゃ想像力をかき立てられますよね。
何者にもなれず日々の生活に流されていく会社員。記事のタイトルにいれた「社会にでてから二度死ぬ」の意味を腹の底から受け入れないといけないステージになりました。
著書の中でも屈指の至言です。
とはいえ読書は読書。心を引っ張られ過ぎず吸収出来る事は吸収し、一応はまだ続いていく「ゲーム」を続けていく所存です。自分なりの精一杯で。
では!